小池一番町辺りは、昭和の初めまで「京塚」と呼ばれていました。これは「経塚」というのを嫌って「京塚」の文字を使っていたようです。昭和初期の区画整理の時に塚が壊されて道路になりました。
昔、旅をしながら修行をしていた一人の坊さんが、小池の村にさしかかりました。ちょうど真夏の頃であったので、のどが大変渇いておりました。一軒の百姓屋に寄り、水をひとくち飲ませてくれるように頼みました。ところが、長い旅で身なりはすっかり汚れ、あまりもみすぼらしいので、その家の嫁は一滴の水も与えずに追い出してしまいました。次の家もやはり同じでした。坊さんは村人の信心の薄さに嘆きながら村を立ち去りました。
その坊さんは、新吉町の竜拈寺や豊川の妙厳寺、越前の永平寺などで修行を重ね、高い位の坊さんになりました。偉くなった坊さんは、5人の坊さんを従えお駕籠に乗って江戸に帰る途中、また小池の村を通りかかりました。すると、あの二軒の百姓屋がそろって葬式を出していました。
あの百姓屋の嫁が、二人とも変な病気にかかり、いくら水を飲んでものどの渇きが治らず、気違いのように水を欲しがってとうとう死んでしまったというのです。お坊さんはふびんに思い供養のためにねんごろにお経を上げ、そのお経を地中に納めて塚を築きました。
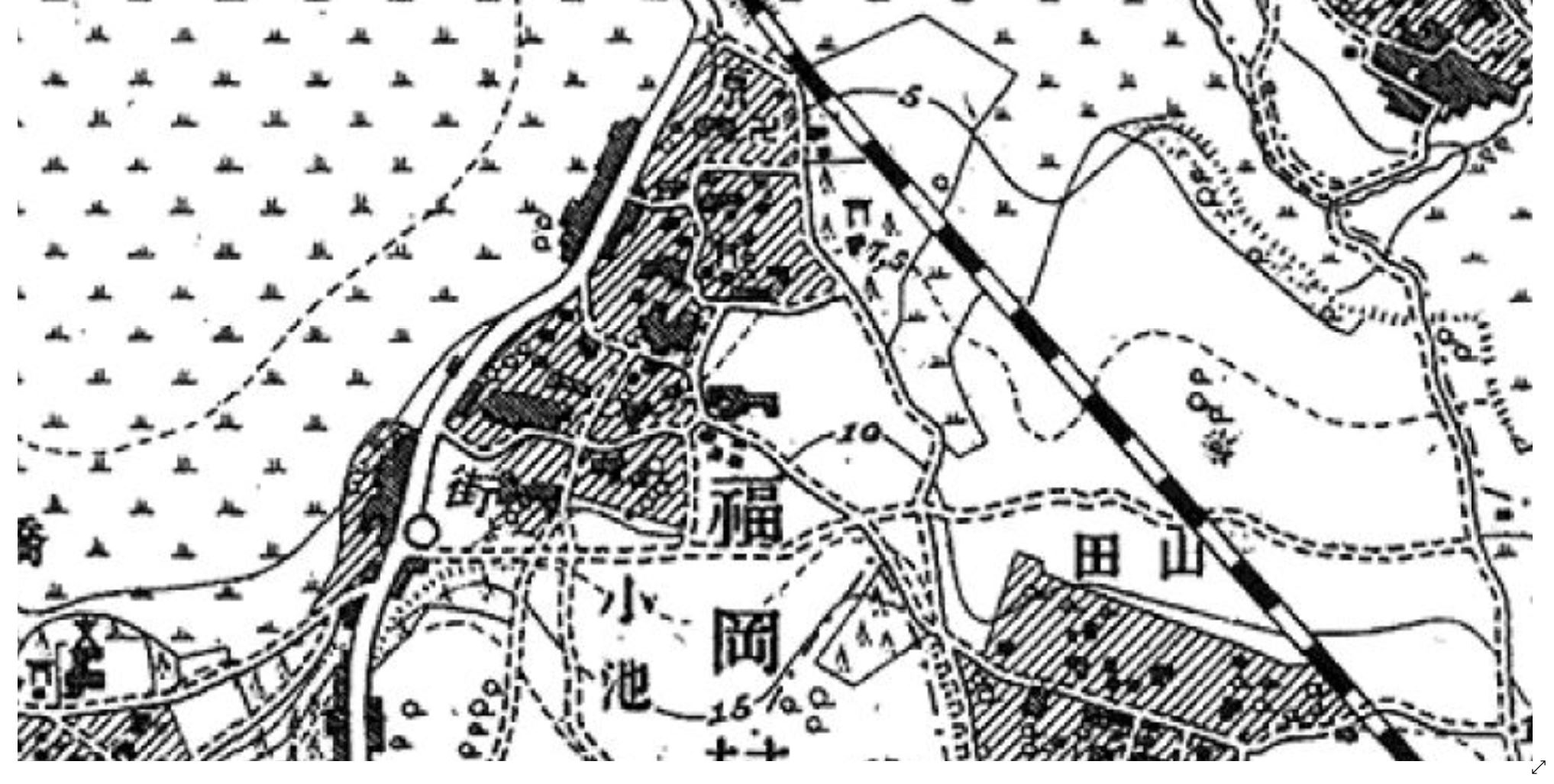


コメント